バックナンバー第101回~第110回
第101回 ”サンタクロースを信じない人”にオススメ
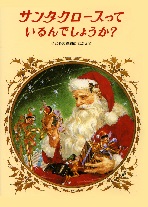
図書館 学生アルバイト 福田倫世
私のオススメ
『サンタクロースっているんでしょうか?』
ニューヨーク・サン新聞社説/中村妙子訳/東逸子絵
偕成社 1986年10月
小さな子供に「サンタクロースは本当にいるの?」と聞かれたとして、その時あなたはどう答えますか?嘘を教えてはいけません。「いる」と答える?「いない」と答える?遡ること100年以上前、そんな難しい質問に、ぴたりと答えた人がいます。
この本に記されているのは、8歳の少女バージニアからの「サンタクロースっているんでしょうか?」という質問に、投書に答える形で新聞に掲載された、ニューヨークのサン新聞社からの返事です。それは彼女に当てた手紙であり、ニューヨーク・サンの社説でもあります。今から100年ほども前に書かれ、今なお語り継がれるこの名社説で、記者は「サンタクロースはいる」と答えたのでしょうか?ぜひ、一度読んで確かめてみてください。
目に見えないもの、信じる気持ちと想像力、大人になるにつれて忘れてしまう大切なことを教えてくれる一冊です。
第102回 見てはいけない世界に惹かれてしまう人にオススメ
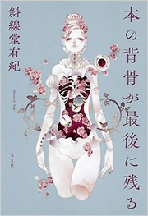
図書館 学生アルバイト 生駒美怜
私のオススメ
『本の背骨が最後に残る』
斜線堂有紀著
光文社 2023年9月発行
この本は表題作である「本の背骨が最後に残る」以外にも「死して屍知る者無し」「痛妃婚姻譚」「本は背骨が最初に形成る」などの七編が収録されています。
どのお話も独特な世界観で、作者さんのアイデアや創造力に感動する一方、残虐なシーンが多いので、読んだ後かなり心に傷を負います。それほど、過激なシーンが多いにも関わらず、いつのまにか、残酷さと美しさが共存している不思議な世界観に魅了され、読むのがやめられなくなってしまいます。
私のように、ホラーが苦手なのに話が気になって結局最後まで見てしまった、というような経験がある人はきっとこの世界観にのめりこんでしまうと思います。
グロテスクな描写に話の印象を持っていかれそうになりますが、美しく切ない、すばらしい作品なので、ぜひ一度読んでみてください。
第103回 いろいろなことにいっぱいいっぱいになっちゃっている人にオススメ

図書館 学生アルバイト 嶋田光紗
私のオススメ
『しないことリスト』
pha著
大和書房 2016年1月発行
生きていると「しなきゃいけないこと」で溢れていていっぱいいっぱいになることが無いでしょうか。“勉強とお家での家事を両立させないといけない”“健康のために運動しないといけない”“予定は守らないといけない”…考えてみたら目の前にある課題から、無意識に守っている当たり前だと思っていること、生きていく中でいろいろな「しなきゃいけない」が存在します。……でも本当にそれって根を詰めてまでしないといけないことでしょうか。この本は〈いわゆる「しなきゃいけないこと」の99%は「本当は別にしなくてもいいこと」だ。〉心に余裕を持つために大切なのは自分の価値観であり、自分のペースを理解することだ、という考えの基、36個の「しなくてもいいこと」がぎゅっと詰まった1冊です。
「イヤなことをしない」「感情を殺さない」「家賃を払わない」など確かに無理してしまいそうだなという項目から、そんなことも「しなくていいこと」なの⁉と思うようなタイトルまでいろんな項目があります。先に述べているように私は「家賃を払わない」がはじめ見たとき衝撃を受けて読んだのですが、分かりやすく表現が好きでとても面白かったです。自分の好きなところから好きなペースで読むことが出来るので、ぜひ読んでみてください。忙しいという方も良ければ手に取って少しでも興味がわくなあという項目を見つけられましたら読んでみてください。
第104回 思いが伝わる言葉を使いたい人にオススメ

図書館 学生アルバイト 岡野 凛
私のオススメ
『伝える準備』
藤井貴彦著
株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021年7月発行
私のバイブルをご紹介します。
皆さんは人に何かを伝えたい時、言葉をかけたい時、何と言うのが一番良いのか悩んだ経験はありませんか?
この本は、アナウンサーの藤井貴彦さんによる、その日のニュースをいかに視聴者に伝えるか、どんな風に「伝える準備」をしているのかが書かれています。言い方、伝え方、準備の仕方次第で、聞き手の受け取り方(=自分への印象)は大きく変わることを教えてくれます。
例えば、
「その文章、あんまり面白くない。」 「今日のきみの仕事はいまいちだった。」
これらの言葉をポジティブな言葉に変換してみると、どんな言い方になるでしょうか。藤井さんなら、こう言います。
「あと少しで合格点かな。」 「いい時と比べると、惜しいね。」
思ったことをただ単にそのまま伝えるよりも、聞き手のやる気やプライドに傷をつけずに、“もっと頑張ろう” と思える言葉ではないでしょうか。
どんな言葉を、どんなふうに使うかで、あなたの印象はつくられます。
発した言葉が、あなたをつくるのです。 (p.8)
「伝える準備」のプロ・藤井貴彦さんが、多くの時間をかけて言葉を選び抜いた「伝える準備」のススメが、この一冊には詰まっています。思いが伝わる言葉を使いたい、春から新しい環境で頑張りたい皆さんに、とっておきのおすすめ本です。
第105回 自分を変えてくれる素敵なことばに出会いたい人にオススメ
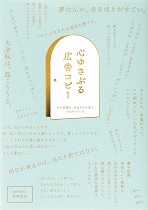
図書館 学生アルバイト 佐藤 綾
私のオススメ
『心ゆさぶる広告コピー その言葉は、あなたの人生とつながっている』
作品選定・解説文 岩崎亜矢
株式会社パイ・インターナショナル 2021年6月発行
広告をじっくり見たことはありますか?店頭や電車の中、新聞や雑誌など、広告と触れ合う機会は普段の生活の中で思ったよりもあると思います。けれど、普段それに注目することはほとんど無いのではないでしょうか。たかが広告と思うかもしれませんが、だからといって通り過ぎてしまうのは勿体ないと思います。
この本は、読み手が共感し心動かされるような広告コピーを集めた名言・作品集です。
「夢なんか、あるほうがすごい。」(p.16)
「走れ、母のお腹を蹴っていたその足で。」(p.30)
「思い出だって、思い出さないと消えてしまうから。」(p.106)
どんな広告か分かりますか?このような、なにか訴えかけてくるようなことばが「わくわく」「うるっと」など感情ごとに分けて紹介されています。広告は告知や宣伝などに使われるものですが、だからこそ、人を惹きつける力があります。ことばのプロが試行錯誤し、想いが凝縮された広告コピーは、短い文章から物語や大きな世界を想像することのできる作品であると思っています。
また、このように「惹きつけられることば」は、広告やデザイン以外でも役に立ちます。スピーチやプレゼン、面接など、短い文章で自分の想いを伝えたい場面はいくらでもあります。そんな時のためにも、読んでおくべきではないでしょうか。
広告は多くの人の想いと知恵が詰まっています。だからこそ、きっと自分に響くことばが見つかります。
第106回 人との違いに悩んでいる人にオススメ
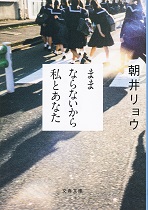
図書館 学生アルバイト 道山萌
私のオススメ
『ままならないから私とあなた』
朝井リョウ著
文藝春秋 2019年4月発行
人との違いに悩んだことはありませんか。
友達や先輩、後輩、そして、家族、バイト先の人など大学生になって関わる人が増えたことによって、人との違いも感じる場面も増えてくると思います。ですが、関わらずに生きていくことはできません。その中で、人との価値観の違いや能力の違いなどに悩まずにもいられません。そんな人におすすめしたい一冊です。
この一冊は「レンタル世界」と「ままならないから私とあなた」の二篇から構成されている一冊です。「レンタル世界」のあらすじは近年、なんでも便利にレンタルできる時代になってきた世の中で人間までもレンタルする時代に突入しています。どこまでが本当の人間関係でどこからがレンタルなのか改めて自分の周りを疑ってしまうような内容です。また書名にもなっている「ままならないから私とあなた」のあらすじは小学生のころから友達の薫と雪子が中学、高校、大学そして、社会人へと成長していく中で自分の価値観と相手の価値観の違いに悩み、読者側も自分らしさとはなにかを考えてしまうような内容です。
この本を何か断定的な言葉で表すことはするべきではないと思い、あまり自分の感情を入れずにおすすめしてみました。ここであえて断言するなら、この本を読み終わった後の感じ方は誰とも共感しない方がいいと思います。それは、人間一人一人が価値観に違いがあるからです。皆さんには、ぜひ自分で読んで頂いて、感情がどのように動かされるのか、“ままならない”というという言葉をどのように捉えるのか、体験してほしいです。
第107回 つい他人と自分を比べてしまう人にオススメ
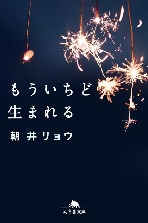
図書館 学生アルバイト 生駒美怜
私のオススメ
『もういちど生まれる』
朝井リョウ著
幻冬舎文庫 2014年4月発行
今回、私が紹介する本は朝井リョウさんの「もういちど生まれる」です。5人の若者を主人公とした短編集なのですが、登場人物がリンクしており、5つの全ての話を読むことで、それぞれの話の主人公や登場人物の内情をより深く理解することができます。ある話では憧れや頼りになる存在として見られている登場人物も、別の話では「こうありたい」「こう見られたい」という理想と、現実の自分の姿にギャップを感じて苦しむ主人公として描かれています。また、自分の可能性を信じられず、何者かになろうと努力する人を小ばかにしている主人公は、別の話では苦悩する主人公の心のよりどころとなっていたりします。この小説は、ある人物が見せている一面がその人の全てではないし、どんなに幸せそうでうまくいってそうでも、人はそれぞれ他人からは見えない痛みを抱えているということを痛感させてくれます。
私たちは常に他人と比較し、比較されながら生きてしまいがちです。あの人は自分と違って才能がある、美人だ、幸せそうだ、頭がいい、人と違ったものをもっている、など他人に対して一方的にコンプレックスを抱いてしまうこともあります。しかし、そうやって羨望をむけられている人たちも、その人なりの苦しみを抱えていて、理想とはかけ離れた自分に失望し、コンプレックスを抱いていたりするものです。それと同時に、ダメだと思っている自分が実は誰かの心の支えになったり、励ます存在だったりすることもあるでしょう。
この小説は必要以上に劣等感を感じる必要はないし、もっとフラットに人と関わってもいいんだと思わせてくれるとても素敵な作品です。
つい人と比較してしまってつらくなってしまう人にぜひ読んでもらいたい一冊です。
第108回 いろんな言葉に出会いたい人にオススメ

図書館 学生アルバイト 嶋田光紗
私のオススメ
『名前のないことば辞典』
出口かずみ著
遊泳舎 2021年2月発行
情や状態、動作を表現する言葉として「オノマトペ」が存在します。どきどきする本、わくわくする冒険、あつあつのグラタン……日常でも使ったり目にしたりすることが多いのではないでしょうか。目にしたとき、口に出そうとしたとき、それらの意味を毎回考えますか?この本を読んだとき、オノマトペは何となく意味が分かっていて、相手にも共通して何となく伝わる言葉だなあと改めて感じました。そんなオノマトペがぎゅっと詰まっている一冊です。意味と例文のまとめられた項目が並んでいます、と言うと辞書みたいに感じられるかもしれません。そんなことは無く、くすくすっと笑ってしまうような例文と、それらの項目を用いた物語やコラムなども含めて普段何気なく使っている言葉やなかなか耳にしない表現に出会うことが出来るのではないかと思います。例えば私が一番好きだと感じた項目が以下の文章です。
[すくすく] 人や動物、植物などが順調に育つ様子。
【例文】「いいねぇお宅の子。すくすく育ってるじゃないか」近所のおじいさんは、いつもどこで買ったかわからないあめをくれます。
言葉の意味に合わせた文章とそれに付随する日常風景が書かれており、今挙げた文章だと言葉の意味にあわせつつ、少し突拍子の無い「どこで買ったかわからないあめ」が登場して面白くて大好きだと感じました。
いろいろな言葉に出会いたい人、なんとなくお話が読みたいけど長編や難しくない本がいいなあと思っている人、そんな風に思っている方がいればなんとなくこの本を開いて何気なく繰り広げられる言葉の海とちいさな物語の世界をのぞいてみてはいかがでしょうか。
第109回 青く暗い夏を体験したい人にオススメ
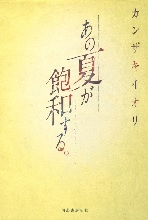
図書館 学生アルバイト 松田杏香
私のオススメ
『あの夏が飽和する』
カンザキイオリ著
河出書房新社 2020年9月発行
「千尋。あんただけは生きて。生きて、生きて、そして死ね」あの夏、逃避行の果てに流花は自ら命を絶った。
あれから十三年。 映画のワンシーンのような流花の最期は、未だ千尋の記憶に色濃く残っている。 彼女の最期の言葉が、彼の頭の中にこびりついていた。 そんなある日、千尋は流花の生き写しのような少女「瑠花」と出会う。 流花を助けられなかった後悔があった千尋。破滅へと向って行く瑠花とその同級生の武命に過去の自分を重ね、救うことを決意する。 自らが辿ったような悲劇へと向かって行く二人を、千尋は止めることが出来るのか――。
カンザキイオリ氏の楽曲「あの夏が飽和する」と繋がるオリジナル作品。 曲を聴くことでより世界観に入れると思います。 彼らは命をかけた逃避行の末に何を見て、何を知ったのか。 命をかけたひと夏の闘いを是非味わってみて下さい。
第110回 異世界ファンタジーが好きな人・苦手な人にオススメ
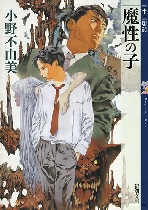
図書館 学生アルバイト 佐藤綾
私のオススメ
『十二国記』シリーズ(全15巻)
小野不由美著
新潮社 2012年7月-2019年11月発行
このシリーズの舞台は、慶・奏・範・柳・雁・恭・才・巧・戴・舜・芳・漣という12の国が幾何学模様のように配置されている中華風の異世界であり、それぞれに、天の意思を受けた麒麟に選ばれた王が麒麟や官吏、民たちとともに国を治めています。このように、それぞれの国の王や麒麟、そこに関わる人々を主人公とした作品集です。
私はエピソード1である『月の影 影の海』から読み始めましたが、これは、日本から突然連れ去られ異世界に来てしまった高校生陽子が、苦難に満ちた冒険を経て、成長しながら王を目指していく話です。上下巻ありますが、なかなか希望が見えません。追い詰められていく陽子がどのようなことを知り、どのような選択をするのかが非常に興味深い作品です。
ファンタジーを苦手に思っている人はいると思いますが、この作品は、そんな人にも読んでもらえると思っています。ファンタジーというと、魔法を使うような世界を連想しますが、このシリーズでは「魔法」は存在しません。異世界でありながら背景設定が綿密に練られているため、どこかリアルに感じることができます。
『月の影 影の海』の解説を行った北上次郎氏は「ファンタジーを苦手とする私がぐいぐい読まされたのは、それらのファンタジックな設定が物語の衣装にすぎないからだ」(p.262)と言っており、状況設定と巧みなストーリーの背後にある、全シリーズを通して共通して流れている「人が人として生きる上の本文とは何か」「信義とは何か」「人を信じるとは何か」といった太いテーマがあるからこそ、感動と感銘があると述べています。
また、十二国記シリーズに関して、『魔性の子』という作品がありますが、これは、発売当初はシリーズではなく長編ミステリホラー小説でした。しかし、その後十二国記がスタートし、シリーズが進んだことで実は番外編であったことが分かりました。そのような背景から、全シリーズを通しての主人公がエピソード1の主人公である陽子なのか、エピソード0の主人公である高里なのかは読者によって変わってくるそうです。このように、シリーズが始まる前からシリーズの伏線があったという展開には驚かされました。
十二国記は、風景描写や登場人物の感情の変化などが細かに描かれているため、より鮮明に物語を想像しながら読むことができます。人によっては、くどくどしていて読み難いと感じてしまうかもしれませんが、そこが小野不由美さんの作品の良いところであり、それが作品の雰囲気を作っていると思っています。飢餓や貧困、反乱や謀反、王座簒奪がはびこる異世界を冒険しながら、小野不由美節の効いた作品をぜひ楽しんでください。



